2023/02/12 受難節前第二主日 使徒言行録説教第44回
共に救いを仰ぎ見る 15章1~11節 牧師 上田彰
*召された時の身分のままで歩みなさい
ドイツに留学して最初の頃の話です。まだ語学学校に通っている間は、色々な分野の外国人と友達になることが多いものです。クラスの友人の紹介で、一人のエチオピア人と会うことになりました。なんでも、私がキリスト教の牧師だというので、牧師なら会ってみたい、私もキリスト者なのだ、ということのようです。何の分野の勉強をするためにドイツに来たのかは忘れましたが、年齢は私より少し上といった感じの男性です。聞くところによると、本国であるエチオピアにいる間に、海外から来たプロテスタントの宣教師から洗礼を受けてキリスト者となった、ということだそうです。以下はその方の話です。
自分は元々はイスラム教徒だった。その時には奥さんが4人いたのだが、洗礼を受けてからはその内三人とは別れて、今は一人の愛する女性と共に過ごしている。だから私はハッピーだ。そんな話でした。
丁度その頃は近くの町に、私より3年ほど早くドイツでの留学を始めた小泉先生という、以前から親しくしている日本人牧師が住んでいました。それで私の方の語学学校の授業が終わってから、向こうの大学の授業が終わっていたら時々町中で会って喫茶店で話したりしました。その日会ったエチオピア人との話をしたところ、次のように小泉先生はおっしゃるのです。「いや、それはおかしい。その人はイスラム教徒である間に結婚した人と、キリスト者になったからといって別れる必要は無いはずだ」、と。言われたら私も気がつきました。パウロは「召された時の身分のままで歩みなさい」と第一コリント7章で語っています。その意味は、洗礼を受けたときに独身であれば独身のまま、洗礼を受けたときにキリスト者ではない人と結婚していればそのままでいればいい、という意味だと理解されています。もちろん当時と今とでは社会状況が全く違うので、キリスト者はキリスト者とでないと結婚してはならない、というような意味ではありません。ただ、主に出会ったときの状況を受け入れ、そこから出発すべきだというパウロの趣旨は汲んでおく必要があります。したがって、小泉牧師が言うように、イスラム教徒として複数の女性と結婚をしたのちにイエス様に出会って洗礼を受けたのであれば、わざわざ離婚をする必要は無いとも考えられます。
一応一つだけそのエチオピア人の肩を持っておくと、彼が四人の妻がいたうちで三人と離婚してハッピーだと言っていたのは、もう飽きたからだとかそういう話ではなくて、イスラム教社会における女性の地位の低さということが背景にあるのかも知れません。コーランの中では複数の妻と結婚している者はそのすべてを平等に愛さないとならない、と書かれていますが、その通りに実践している人はほとんどおらず、最初の奥さんに飽きたから次の奥さんと結婚する、という風になっていることがほとんどなのだそうです。その人の場合にどうなっていたかは分かりませんが、周りにそういった女性蔑視を前提にした結婚生活を営んでいる人が大勢いたのはほぼ間違いなく、それに対して彼はキリスト者となったことをきっかけにして、たった一人の女性だけを愛する生活を始めた、だからハッピーだと言ったのだ、そういう風に考えることが出来ると思います。
さてそれから半年ほどして私も晴れて語学学校を終え、大学に入りました。そこで研究室に、イスラム教のことに詳しい神学生がいたので、その人にイスラム教からキリスト教に転向した人の結婚ステータスについてどう考えるべきか、尋ねてみました。するとその神学生は、少し肩をすくめて、ちょっと意外なことを言い始めました。「私はイスラム教徒がドイツに来て自分たちの国の慣習をそのまま持ち込むことがドイツに混乱を起こしているように思う。だからイスラム教徒の男性が複数の女性と結婚した状態で、つまりイスラム教徒のままでドイツで生活を始める場合、戸籍上は最大で一人の女性との結婚だけが法的に確認される婚姻状態であり、それ以上の女性については愛人というような形になる。確かに外国人女性が夫のビザによる裏付け無しにドイツに滞在することは難しい。しかしそれは「夫」の側の問題であり、夫はそこまで配慮してドイツに来るべきだ。それが嫌なら母国に帰るべきなんだ」。
私はそれまで、ドイツというのは日本に比べて移民に対してはるかに寛容な国だと思っていましたから、イスラム教に詳しいその神学生の友人がイスラム教に対して厳しい態度を取ったことに驚きました。しかし気を取り直して、イスラム教徒の外国人の複数の女性の結婚の話ではなく、元イスラム教徒で今はキリスト者という人が複数の女性と結婚しているという可能性についてどう考えるか、と聞いてみることにしました。これは事実上、ドイツ人が、いわば小細工をした後ドイツに戻ってきて、複数の女性と結婚した状態でドイツ社会の一員として過ごすことが可能か、と聞いていることになります。当然これまでの文脈でおわかりのように、彼は、「そんなことは認められない」と言いました。「もしそれが認められるなら、ドイツ人のキリスト者が一旦外国でイスラム教に改宗して、それで複数の女性と結婚をし、またドイツに戻ってキリスト者に戻ればドイツ人が複数の女性と法律上の結婚が出来ることになる。そんなバカな話はない」、というのです。
*割礼を受けて、洗礼を受けて、救われる
この話は、当時から20年経って改めて考えてみると、そもそも「召される」とはどういうことか、という問題であることに気づかされます。因みに先ほどの、召された時の身分で、という箇所は、パウロが異なるテーマを三回挙げながら、三回繰り返して「召された時の身分に留まりなさい」と言っているところです。ご興味のある方もおられるかと思うので、7章の解説をすると、まず信者である妻が、未信者である夫と信仰のことで諍いになった場合に、離縁をすべきかどうか、という問いがパウロの元に寄せられたようです。それに対するパウロの答えで、かいつまんで言うならば、どうしても無理なら離縁もやむを得ないが、しかし結婚というのは導きなので、一度結婚したのにそれは聖なる結婚ではなかったとあとから言って離縁する必要は必ずしも無い、今の状態を召された状態、導かれた聖なる状態だと信じてまずは受け入れなさい、と言っています。つまり結婚というのが召されたものである、というのが一つ目です。次に出てくるのが割礼で、割礼を受けた者が洗礼を受けた場合、割礼をなかったものとする必要は無い。しかし割礼を受けていない者が洗礼を受ける場合に、わざわざ割礼を受けてからという順番を取る必要は無い。割礼というのをその人は召しとして受けたはずで、それを否定する必要は無い。しかし今は洗礼を召しとして受け止めているのだから、むしろそちらを重んじなさい。割礼を受けたという歴史を否定する必要は特にない。さらにその後、パウロは19世紀アメリカの奴隷解放論者が聞いたら怒り出すようなことを言っています。それは、あなたが奴隷として召されたなら奴隷として仕えるのが召しなのだ、と言います。これは恐らく、鎖を嵌められて強制労働を課されていた近代の黒人奴隷のあり方と大きく異なる、職業としての奴隷であったキリスト者、おそらくは借金が理由で奴隷になった信仰者から、私の主はイエスキリストお一人なのだから、奴隷をやめられるものならやめた方がいいのか、という問いへの答えだと思います。パウロは繰り返し三度、召された身分に留まりなさい、と語ります。
今日の話は従って、今申し上げた三つの問答の内の、二つ目に関わる出来事と関わっています。「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と言い出したユダヤ人キリスト者がいたというのです。この15章は、使徒言行録の中でもいくつかある、重要な章の一つです。何回かに分けて見て参りたいのですが、その中で今日はイントロのような話です。
先ほどの、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」という言葉ですが、言い出したのはエルサレム周辺からやってきた、元々はユダヤ人であった、今はキリスト者となっている人の言葉です。いきなり洗礼を受けてキリスト者となるのではなく、まず洗礼を受ける前にユダヤ人となるべく割礼を受けてから洗礼を受けなさい、という趣旨の言葉です。
*救いのための便宜的措置?
この言葉について考えていたときに、冒頭で話したドイツにおける元イスラム教徒のエチオピア人キリスト者の話を思い出したのです。何か、似ている構造があります。ドイツ人のイスラム教嫌いの神学生は、こう語りました。もともとキリスト者であるドイツ人が、複数の奥さんと結婚したいからといって便宜的にイスラム教徒になることは、公平の観点から言って問題がある。
これは次のような言い方にすれば今日の聖句に出てくるユダヤ人の言葉と同じ構造になるのではないでしょうか。異邦人が、つまりユダヤ人でない者がユダヤ教の一派であるナザレ派に属する場合には、一度割礼を受けなければならない。最終的にイエス・キリストの名による洗礼によって教会に所属することを希望する場合であっても、割礼を便宜的に受けることは必要だ。

つまり、キリスト教とイスラム教の間には、便宜的にお互いの宗教に改宗したりするような間柄は存在しないが、ユダヤ教とユダヤ教ナザレ派としてのキリスト教との間には、便宜的な改宗を認める関係性がある、というのが一節に出てくる人たちの主張なのです。それに対して、いやいや、そんな関係性などそろそろなくなってきているはずだ、という意見がありました。そんなことを決めるのが15章の、通称「エルサレム会議」なのです。その会議のきっかけになったのが、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」という言い方なのです。通常は割礼というのは小さな子どもに対して行うものですが、大きくなってから行うことも出来ます。ユダヤ教に改宗する際に必要な手続きということです。問題になるのは、それを受けなければ救われない、という言い方です。
ここに出てくる「救う」という言葉は、「救う」と訳せる言葉が聖書にいくつかある中で、「元通りにする」というニュアンスの言葉です。ある翻訳では福音書の中で、「あなたの信仰があなたを救った」というイエス様の言葉を「直した」と訳しています。恐らく、割礼を受けないと、終わりの日に父なる神の審きに耐えることは出来ない、というような大それた意味合いではありません。もともと、終わりの日の審きを避けるために割礼を受ける、というような考え方が強調されていたとも考えられません。もしそのように考えていたとしたら、まるで、その割礼を勧めるユダヤ人達は、審きを行う当事者である神様自身になってしまったかのようです。彼らはそんな大業なことを言いたいわけではなく、むしろ割礼を受けてから洗礼を受けるというのが「マナー」なのではないか、もし洗礼を受けることを大事だと思っているとしても、割礼を便宜的に受けてもいいではないか、というニュアンスで言っているように思います。勧めているユダヤ人達自身の本心は分かりません。本当は割礼の方が大事だと考えている可能性は高いのです。しかし、割礼の方が大事だと考えなさいとまですでに心はキリスト者になっている人たちに言ってもしょうがないだろうと考えていて、そこで身も心もキリスト者になるというよりは、心はキリスト者になっていいから、身の方はユダヤ教に残しておいたらどうか、これはあくまで便宜的な措置だ、と言って説得を試みているのです。

便宜的、というのは都合の良い誘惑の言葉だと思います。福音書の中でも、敵対者たちのイエス様への誘いかけは常に「便宜的」ということを含んでいました。ローマ帝国という共通の敵と戦うために手を組もうではないか、その際、私たちの主張である、食事前と後で二回手を洗うという主張に同意したことにして弟子たちにそう命じてくれ、とイエス様にファリサイ派は提案するのです。しかしイエス様からこの提案は結局拒否されます。あるいはお前は神の子だと自称するのか、それを撤回したら十字架につけることは免れさせてやる、とイエス様は総督ピラトに問いかけられますが、これまた拒否なさいます。さらに遡るなら、荒野で40日飲まず食わずの状態になったイエス様に対して悪魔は、石ころからパンを作れ、飛び降りても死なないところを見せろ、私を拝めば世界を手渡すことにしよう、と提案をします。
本心からファリサイ派の主張に従う必要は無い。便宜的に、見た目だけ少し合わせてくれればいい。
本心から総督ピラトの問いかけに同意する必要は無い。便宜的に、神の子だという主張を撤回してくれればいい。
本心から悪魔に従う必要は無い。便宜的に、ちょっと悪魔に頭を下げてくれればいい。
二つの考え方があると思います。大きな目的であるのは洗礼で、その洗礼に至るために小さなご都合主義、つまり割礼を受けて周りに一応合わせておいたとしても、自分の中で洗礼が大事だということが変わっていなければ別にかまわないのではないか、という考え方が一つはあります。もう一つが、いやいやそんなことをすると、小さなご都合主義がいつの間にか大きくなってしまって、大きな目的が見えなくなってしまうのではないか。今で言えば、人々からはいつまで経っても教会というのはキリスト教などという独立した宗教ではなく、ユダヤ教ナザレ派と言ってユダヤ教の一派なのだ、その証拠に彼らは割礼を受けているではないか、と言われ続ける怖れがあったのです。そうならないために、つまり大きな目的が小さな便宜的措置によってかき消されないようにするために、便宜的措置などというご都合主義的なものはあらかじめ排除しておいた方がいい。エルサレム会議で議論された中心的な事柄は現代にも通じる問いであるように思います。
今日から始まるエルサレム会議の非常に重要な論点は、洗礼というのはそれ自身で完結しているのか、それとも洗礼に至る小さな橋渡しとしての割礼が必要か、ということですが、それは結局の所、ユダヤ主義者の主張というのは、洗礼を受ける前に小さな橋を通る必要がある、その際にはイエス様が私を招いて下さっているという思いを一旦封印して、神殿に思いを向けて割礼を受け、その後またイエス様の方に思いを向けることにしよう、という何か器用な小技を要求することになっているのです。それは戦時中、宮城遥拝という形で礼拝前に皇居の方にお辞儀をしなければならなかったことと重ね合わさるかも知れません。宮城遥拝の必要が無くなった戦後になっても、世間的なブームに合わせるような仕方でないと伝道が出来ないと思うようになっている、という意味で、日本の教会、いえ宗教全体に大きな影を及ぼしているように思います。
*洗礼への思いは、神さまから与えられる
一つのエピソードを思い出しました。戦後のカトリック教会は皇室やその周辺への伝道を熱心に行いました。宮内庁にはかなりの数のキリスト者が務めているとも聞きます。その伝道は相当程度まで皇室に入り込み、ついには後に昭和天皇になる人が皇太子時代、縁談が進んでいた製粉会社の娘さんが、おそらくは軽井沢でテニスデートをする前後に、洗礼を受ける直前の段階にまでなりました。しかし洗礼を受けるというのが縁談の障害になることが十分にあり得る状況です。そこで彼女は密かに教会の司祭に相談をしました。すると司祭はこう答えたというのです。あなたにこれから、極秘の洗礼を授けよう。そのことはあなたと私だけが知っている事柄である。そう言って美智子さんに洗礼を授けた、らしい、というのです。その後縁談が進むに当たって彼女の宗教的ステータスが問題になりました。そして調査報告がなされます。教会には行っていた時期もあるらしいが洗礼を受けてはいない、ということが確認されます。これで結婚に支障は無いということになった、というのです。
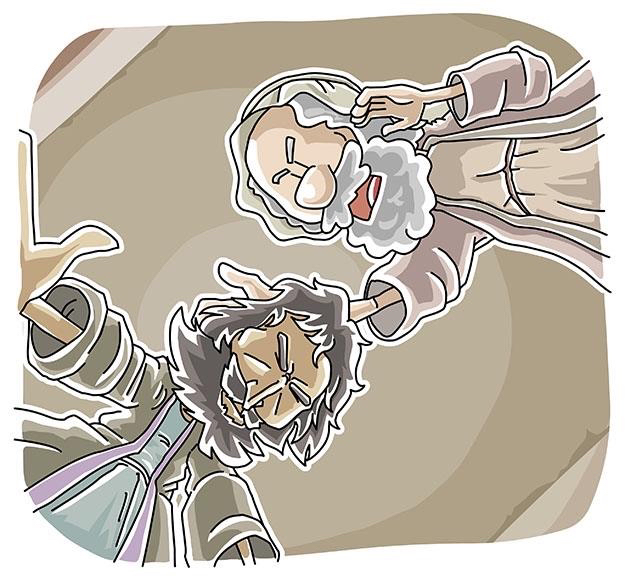
生の授業中の雑談の受け売りです。これを聞いた私は授業中に、うーむと考え込んでしまったのをよく覚えています。美智子妃殿下を隠れキリシタンとして皇室に送り込むというカトリックのロイヤルミッションは、大きな目的は達したということで成功したと言えるのでしょうか、それとも小さな便宜的措置によって絡め取られて大義そのものが失われたと考えるべきでしょうか。
便宜的という言葉の誘惑は、結局の所、あなたは本心から変わる必要は無い、見た目だけ少し合わせてくれればいい、という主張です。しかし割礼を受けるというのは、それほどに簡単なことなのでしょうか。割礼というのは、受けることも出来るけど受けないことも出来る、それを選択するのはあなたの自由であるというほど軽いものなのでしょうか。少なくとも、アンティオキア教会のキリスト者達は、イエス・キリストの名による洗礼については、受けることも出来るけど受けないことも出来る、それを選択するのは私の自由であった、というつもりで洗礼が与えられることを受け入れてはいなかったのです。救いというものに真剣であるということは、救いの前で受け身となることを意味する。ペトロの弁論を聞いてみましょう。いくつかの言葉を抜き書きしてみます。
神がわたしをお選びになった。
神は異邦人にも聖霊を与えた。
彼らの心を信仰によって清めた。
主イエスの恵みによって救われる。
これらはいずれも、救いのしるしとしての洗礼とは、与えられるものであって、受けるか受けないかを選択することは出来ない、ということを言い表しています。洗礼を受けるということと、便宜的なとか小さな橋渡しは、というような話は全くかみ合わない、と彼らは考えていました。
ここではアンティオキア教会におけるパウロやバルナバの弁論については出てきません。彼らは沈黙する形で一つの主張をしています。それは、割礼を便宜的に勧める人たちに対する、ご都合主義的な態度への問いです。これは洗礼を受けようという純粋な思いを踏みにじるものであると同時に、割礼を重んじる生粋のユダヤ人に対する侮蔑にもなるのではないか、そんな主張が聞こえてくるように思います。
来週から数回に分けてこの15章を扱いますが、使徒言行録に記されているのは、この「便宜的」という名の誘惑との戦いであったように思います。
使徒言行録において15章は明らかに一つの山場を迎えていますが、例えばパウロの回心、あるいはステファノの殉教といった山場と並んで有名なのがペンテコステの出来事です。その出来事を、今申し上げた便宜主義との戦いという観点から少し触れておきます。
当時の弟子たちは、あまりにも大きなユダヤ教勢力に怖れをなし、自分たちは家の中に閉じこもって自分たちだけで信仰を続けていればいいのではないか、という思いに陥りかけていました。しかし聖霊の注ぎにより、色々な国の言葉で福音を語ることが出来ることに気づかされたのです。
キリスト教を、世界史の中の小さなエピソードに過ぎないものとしようとする誘惑はいつでも存在します。私たちの人生の中で福音はちょっとした通過点に過ぎないものにしようという誘惑だってあるに違いありません。しかし私たちには賜物があります。洗礼を受け、あるいは聖霊を受けるということは、私たちの選択ではなく、与えられたものなのです。この一方的な恵みを感謝して受け止めたいと思います。
